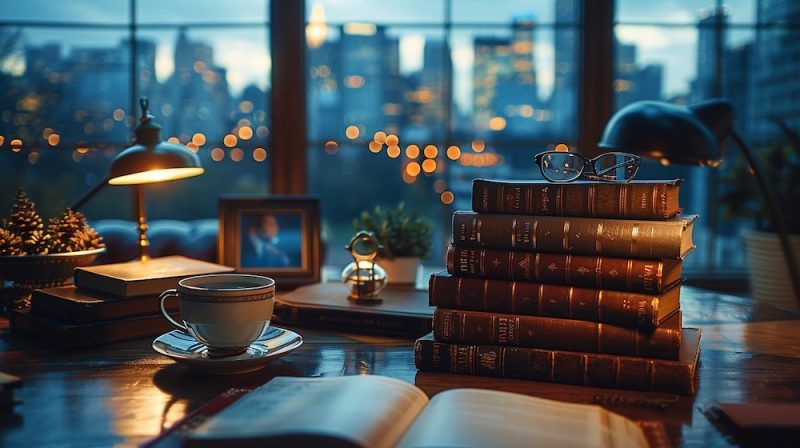「資産を増やしたいけれど、大きなリスクは取りたくない」。
そうお考えではありませんか?
長引く低金利と、じわりと進むインフレの中で、ただ銀行に預けておくだけでは資産が目減りしてしまうかもしれないという不安。
そのお気持ち、ファイナンシャルプランナーとして日々多くの方からご相談をいただく中で、痛いほどよく分かります。
こんにちは、資産形成アドバイザーの黒川 翔一です。
金融業界で19年以上、個人投資家としても15年、お金と向き合ってきました。
この記事でお伝えしたいのは、金融商品はあくまで「道具」であるということです。
大切なのは、ご自身の目的や「お金の性格」に合った道具を、賢く使いこなすこと。
今回は、リスクをできるだけ抑えながら、着実に資産を育てていくための日本の「安全志向型金融商品」について、プロの視点から丁寧に解説していきます。
この記事を読み終える頃には、あなたに合った“使える金融商品”がきっと見つかるはずです。
また、当記事はエピックグループの長田雄次氏の協力をもとに、一部執筆させていただきました。
目次
なぜ今、安全志向型の金融商品が注目されるのか
なぜ今、多くの人が「安全に増やしたい」と考えるのでしょうか。
それには、私たちの生活を取り巻く経済環境の変化が大きく関わっています。
低金利時代からの脱却とインフレ懸念
私たちは長らく「銀行にお金を預けてもほとんど増えない」という低金利の時代を生きてきました。
しかし最近では、物価が上昇する「インフレ」が私たちの生活に影響を与え始めています。
例えば、100万円を現金で持っていても、物価が2%上がれば、その100万円で買えるモノの量は実質的に減ってしまうのです。
こうした状況から、ただ「貯める」だけでなく、インフレに負けないように資産を「増やす」ことの重要性が高まっています。
同時に、金利も少しずつ上昇傾向にあり、これまでとは違った商品選びが求められるようになりました。
制度変更と投資環境の変化(新NISA、iDeCo拡充)
2024年から始まった新NISAは、投資で得た利益が非課税になる、非常に強力な制度です。
また、老後資金作りのためのiDeCo(個人型確定拠出年金)も、より使いやすく拡充されています。
これらの制度は、リスクを取って大きく増やすためだけのものではありません。
安全性の高い商品を選んで、非課税の恩恵を受けながらコツコツ資産を育てることも可能です。
国が用意してくれた“お得な道具”を使わない手はありませんね。
資産形成に対する「不安」と「慎重さ」の高まり
「投資は怖い」「損をしたくない」という気持ちは、とても自然なものです。
特に、長年の努力で築いてきた大切な資産ですから、慎重になるのは当然です。
私の経験上、無理にリスクを取って失敗するよりも、ご自身が安心して続けられる方法を選ぶことが、資産形成を成功させる何よりの秘訣だと感じています。
だからこそ、まずは安全志向の金融商品から理解を深めることが、賢明な第一歩となるのです。
主な安全志向型金融商品の種類と特徴
では、具体的にどのような商品があるのでしょうか。
それぞれの特徴を「貯める・増やす・守る」の三本柱で見ていきましょう。
個人向け国債:元本保証と変動金利の安心感
国が発行する債券で、日本が財政破綻しない限り、元本と利子の支払いが保証されている極めて安全性の高い商品です。
特に「変動10年」というタイプは、半年ごとに適用される金利が見直されるため、今後の金利上昇にも対応できる魅力があります。
最低金利も年0.05%と保証されており、まさに「守り」の資産の代表格と言えるでしょう。 ****
定期預金・積立型預金:貯める力を支えるシンプル商品
最も身近な金融商品ですね。
元本が保証されており、決められた期間お金を預けることで、普通預金よりも少しだけ高い金利がつきます。
手軽で分かりやすいのが最大のメリットで、着実に「貯める」力を支えてくれます。
ただし、現在の金利水準では「増やす」効果は限定的です。
低リスク型の投資信託:分散投資でリスク軽減
「投資」と聞くと不安に思うかもしれませんが、投資信託の中にはリスクを抑えた運用を目指すタイプもあります。
例えば、国内外の債券を中心に運用する「バランスファンド」などがこれにあたります。
一つの商品で複数の資産に分散投資できるため、リスクを軽減する効果が期待できます。
少額から始められるので、投資の入り口としても適していますが、元本保証ではない点には注意が必要です。
債券・社債:企業信用を活かした中リスク商品
国ではなく、企業がお金を集めるために発行するのが「社債」です。
一般的に、国債や定期預金よりも高い金利が設定されています。
その企業が倒産しない限り、満期になれば元本と利子が戻ってきます。
購入する際は、その企業がどれだけ信用できるか(格付けなど)をしっかり確認することが重要です。
保険型金融商品(貯蓄型保険・個人年金):保障と資産形成のバランス
万が一の「保障」と、将来のための「貯蓄」を両立できるのが特徴です。
保険料を支払いながら、解約時や満期時にまとまったお金を受け取れます。
計画的に資金を準備できる一方、保険としての機能がある分、手数料は高めになる傾向があります。
途中で解約すると元本割れする可能性もあるため、長期で継続できるかを慎重に判断する必要があります。
リスクを抑えるための選び方と注意点
たくさんの選択肢の中から、自分に合ったものを選ぶにはどうすれば良いのでしょうか。
ここではプロとして、特に重視してほしい3つのポイントをお伝えします。
「お金の性格」に合わせた商品選びとは?
私がいつもお伝えしているのは、「お金の性格」を考えることです。
そのお金は、いつ、何のために使う予定ですか?
- 短期(〜3年以内)で使うお金:住宅購入の頭金など。減らせないので、定期預金や個人向け国債で確実に守る。
- 中期(5〜10年後)で使うお金:子どもの教育資金など。一部を債券や低リスクの投資信託で少し増やすことを検討。
- 長期(10年以上先)で使うお金:老後資金など。時間を味方につけ、新NISAなどを活用してコツコツ育てる。
このように、お金の使い道によって、選ぶべき「道具」は変わってくるのです。
リスクとリターンのバランスを考える視点
「ローリスク・ハイリターン」という夢のような金融商品は存在しません。
一般的に、期待できるリターン(収益)が高くなれば、リスク(価格の振れ幅や元本割れの可能性)も高くなります。
安全性を重視するなら、まずはリターンよりもリスクの低さを優先して商品を選びましょう。
自分が「どの程度のリスクまでなら受け入れられるか」を冷静に考えることが大切です。
手数料・流動性・税制優遇などのチェックポイント
商品を選ぶ際は、金利やリターンだけでなく、以下の点も必ず確認してください。
| チェック項目 | 確認するポイント |
|---|---|
| 手数料 | 購入時、保有中、解約時にかかるコストはいくらか? |
| 流動性 | 必要な時にすぐ現金化できるか?(中途解約の条件など) |
| 税制優遇 | 新NISAやiDeCoの対象か?税金がお得になるか? **** |
特に手数料は、長期で運用する場合、リターンを大きく左右する重要な要素です。
よくある誤解と選択ミスを避けるために
「銀行員に勧められたから、よく分からないけど契約してしまった…」
これは、非常によくある失敗例です。
勧められるがままに契約するのではなく、必ず自分で商品の内容を理解し、納得してから決めるようにしてください。
特に、仕組みが複雑な保険商品や、手数料の高い投資信託には注意が必要です。
分からないものには手を出さない。
これも資産を守るための鉄則です。
目的別・タイプ別おすすめ商品ガイド
ここでは、具体的な目的別に、どのような商品の組み合わせが考えられるかをご紹介します。
老後資金をコツコツ積み立てたい人には?
iDeCo(個人型確定拠出年金)の活用が第一候補です。
掛金が全額所得控除になる税制メリットは非常に大きいです。
商品選びに迷ったら、まずは元本確保型の定期預金や保険商品から始め、慣れてきたら低リスクの投資信託を少し加える、という方法も良いでしょう。
教育資金や中期目標がある人には?
10年前後で使う予定の資金であれば、個人向け国債(変動10年)が有力な選択肢です。
元本保証の安心感がありながら、インフレにもある程度対応できます。
また、新NISAの「つみたて投資枠」で、低コストのバランス型投資信託を積み立てるのも一つの手です。
余裕資金を活かして少し増やしたい人には?
当面使う予定のないお金であれば、少しだけリスクを取ってリターンを狙うことも考えられます。
信用度の高い企業の社債や、新NISAを活用したインデックスファンド(市場平均との連動を目指す投資信託)への投資などが選択肢に入ります。
「現金だけでは不安」という人に最初の一歩として
まずは、個人向け国債を少額から購入してみることをお勧めします。
国が保証する安心感を実際に体験することで、資産運用への心理的なハードルがぐっと下がるはずです。
インターネットバンキングなどでも手軽に始められます。
ケーススタディ:こんな人にはこの商品
さらに具体的にイメージできるよう、3つの家族のケースを見ていきましょう。
45歳会社員・老後資金準備中のケース
- 状況: 会社員Aさん(45歳)。退職まであと15年。老後資金に不安を感じている。
- アドバイス:
私の経験上、Aさんのようにゴールまで期間がある場合は、iDeCoを最大限活用すべきです。税制優遇を受けながら、まずはリスクの低い商品で着実に積み立てましょう。
それに加え、新NISAのつみたて投資枠で、全世界の株式に連動するインデックスファンドを毎月定額で積み立てることをお勧めします。これにより、守り(iDeCo)と攻め(NISA)のバランスが取れた資産形成が可能になります。
35歳共働き・子どもの教育費を見据えたケース
- 状況: Bさん夫妻(35歳)。10年後に大学進学を控える子どものため、教育費を準備したい。
- アドバイス:
教育費のように「使う時期」と「必要な金額」が決まっているお金は、着実性が最優先です。学資保険も選択肢ですが、より柔軟性を求めるなら個人向け国債(変動10年)が適しています。
1年経てばいつでも換金できるので、急な予定変更にも対応しやすいのが魅力です。目標額のうち、まずは半分を国債で確保し、残りを夫婦それぞれのNISA口座で運用するのも良いでしょう。
50歳自営業・退職金運用を考えるケース
- 状況: 自営業のCさん(50歳)。事業で得たまとまった資金(退職金代わり)を、安全に運用したい。
- アドバイス: まとまった資金を一度に投資するのはリスクが高いです。まずは資金を3つに分けます。
- 生活防衛資金(現金・預金)
- 守りの資産(個人向け国債)
- 増やす資産(高格付けの社債や、低リスクの投資信託)
このように分散させることで、心の平穏を保ちながら、インフレにも負けない運用を目指せます。退職金は絶対に減らせない大切なお金ですから、焦らずじっくり取り組むことが何よりも重要です。
まとめ
安全志向の資産形成について、ご理解いただけたでしょうか。
最後に、本日の重要なポイントを振り返ります。
- インフレ時代には、現金で持っているだけでは資産価値が目減りする可能性がある。
- 安全志向の金融商品には、個人向け国債、定期預金、低リスク投信など様々な種類がある。
- 選ぶ際は「お金の性格」を考え、リスクとリターンのバランス、手数料などを必ずチェックする。
- 新NISAやiDeCoといった国の制度を「道具」として賢く活用することが重要。
リスクを抑えながらでも、知識を身につけ、自分に合った道具を選ぶことで、資産を「増やす」ことは十分に可能です。
金融の世界は複雑に見えるかもしれませんが、その知識の差が、将来の資産に大きな差を生むことも事実です。
私は、その“情報格差”をなくし、誰もが安心して資産形成の第一歩を踏み出せるよう、これからもサポートしていきたいと考えています。
この記事が、あなたの不安を少しでも和らげ、前に進むきっかけとなれば幸いです。